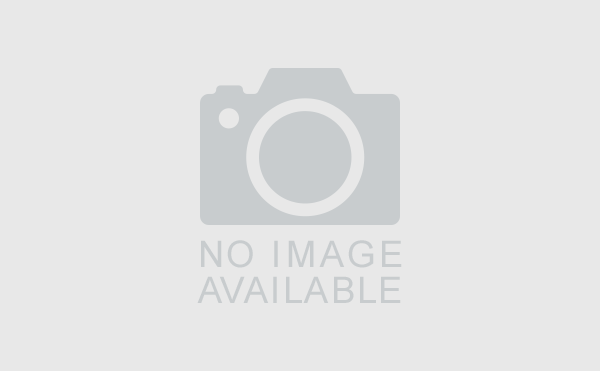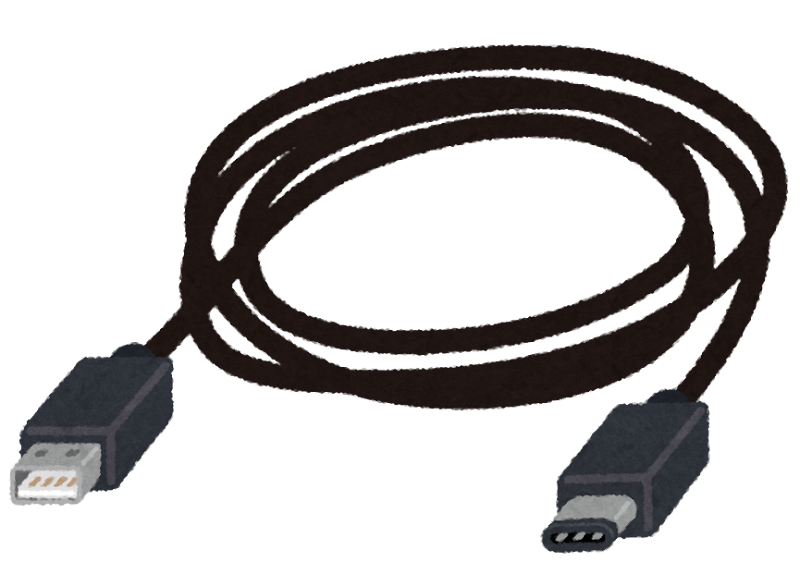回生型ってどうなの?技術現場での使用感を交えて

ニュースでも掲載されている通り、この度 当社の「Ene-phant series®」が「川崎CNブランド等推進協議会」より、2024年度の「川崎メカニズム認証制度」の認証を取得いたしました。これをきっかけに、より多くのお客様に注目されることを期待しております。しかし、電子負荷を選定する際に、通常の電子負荷と比較し「ちょっと高いな」や「使いやすいの?」と感じるお客様もいらっしゃるかと思います。
電子負荷の選定は自動車選びに似ている?
電子負荷の選定は、自動車に近しいものがあると感じております。同じ馬力の自動車でも、電気自動車とガソリン車を比較する際に“価格“はもちろん、燃料を補給する“環境“や実際に動かした際の“使用感”といった点が主な選定基準になるでしょう。電子負荷も同様に、お客様の使用環境によっては回生型が適さない場合もございます。価格と環境については、お客様の方でも変えることができない部分もあるかと思いますので、今回は使用感について少しお話ししたいと思います。
通常の電子負荷 vs 回生型電子負荷の最大の違い
当社の現場では通常の電子負荷と回生型電子負荷どちらも稼働する機会がございます。各製品のスペックについては当社のホームページをご覧いただきたいのですが、両者の最大の違いは消費エネルギーの圧倒的な差にあると思います。ご存じの方も多いと思いますが、通常の電子負荷は自身での負荷を熱に変えて消費するのに対し、回生型電子負荷は負荷を電気として系統へ戻すことで消費を極力抑えるようになっております。「二酸化炭素の消費量削減」といった環境面ももちろん大事ですが、現場で最も違いを感じるのが“暑さ”です。
現場での「暑さ」の違い
当社の得意とする大容量(数十kWクラス)の負荷を通常の電子負荷を用いて継続的に電流を引き続けた場合、一般的な建屋の冷房では太刀打ちできず、夏場はあっという間にサウナ状態になってしまいます。(逆に冬場は暖房いらずとなってしまうのが良いような悪いような話ではあるのですが(笑) )対して回生型電子負荷の場合、多少の熱は発生するものの冷房を入れていれば快適な環境で試験を継続できるかと思います。
今回の話がお客様の電子負荷選定のどこまで参考になるかは分かりませんが、スペックからは伝わりづらい点も考慮しつつ、当社の製品に興味を持っていただけますと幸いです。