Modbusって、そもそもナニ?
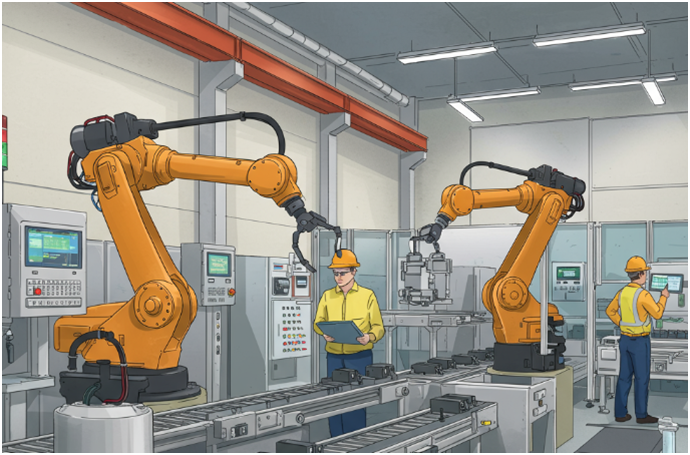
はじめに
Modbusは、簡単に言うと「いろいろな機械や機器同士が情報をやり取りするための共通ルール」であり、主に工場や産業機械の自動化で使われる通信プロトコル(データのやり取りの手順や約束ごと)です。本稿ではModbusについて、わかりやすくご説明します。
Modbusとは?
Modbusは、1979年に作られた通信規格で、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)やセンサ、監視システムなどの機械同士を接続するために開発されました。
たとえば、工場のPLCがセンサから温度を取得したり、電力メーターのデータを読み取ったり、モーターを制御する際に使われます。
ポイント
- 「機械同士が話すための言葉」 と捉えると分かりやすいです。
- 機器をつなげて使用する工場などの現場で広く使われています。
- シンプルで使いやすいため、世界中で採用されています。
合わせて読みたい
Modbusのしくみ
Modbusの仕組みは「主役(マスター)」と「補佐(スレーブ)」のやり取りで動きます。
マスターとスレーブ
- マスター:データを要求する機器(例:PLCやPCなど)
- スレーブ:データを提供する機器(例:センサ、アクチュエータ、計測器など)
マスターがスレーブに対して「今の温度を教えて」とか「この値を設定してください」と指示を出し、スレーブが「はい、温度は25度です」と応答するような流れです。
Modbusの種類
Modbusには複数のバージョン(通信方法)がありますが、主なものは以下です。
(1) Modbus RTU(Remote Terminal Unit)
- シリアル通信(RS-485やRS-232)を使います。
- 「バイナリ形式」でデータをやり取りし、高速で効率的。
- 工場などの現場でよく使われる形式。
(2) Modbus ASCII
- シリアル通信を使うが、データを「文字形式」でやり取りします。
- 分かりやすい反面、RTUに比べて通信速度は遅め。
(3) Modbus TCP/IP
- Ethernet(イーサネット)を使った通信。
- インターネットやローカルネットワークを使えるので、距離や配線が自由。
- 最近では主流になりつつあります。
合わせて読みたい
Modbusのデータ構造
Modbusのデータは「レジスタ」と呼ばれる記憶装置のような領域に保存されています。
主なデータ領域
- コイル:0か1(ON/OFF)の状態を表すデジタル信号。
- 入力ステータス:スレーブから読み取るだけのデジタル信号。
- 入力レジスタ:マスターが読み取れる「アナログ値」。
- 保持レジスタ:マスターが読んだり書き込んだりできる「アナログ値」。
例)
モーターのオン/オフを決めるには「コイル」を操作し、温度センサのデータを読み取るには「入力レジスタ」を参照する、というイメージです。
なぜModbusが使われるのか?
| シンプルでわかりやすい | 難しい設定が不要で、扱いやすいです。 |
| 汎用性が高い | 多くのメーカーの機械や装置に対応。 |
| 低価格 | 導入コストが低く、特別な機器を必要としない。 |
| 信頼性が高い | 長い歴史があり、試行錯誤を重ねて安定しています。 |
具体的な使い方(例)
例1:温度データの取得
- マスター(PLC)がスレーブ(温度センサ)に「温度を教えて」と命令を出す。
- スレーブが「27.5°C」と応答を返す。
- マスターはそのデータを記録してモニターに表示する。
例2:モーターの操作
- マスター(PLC)がスレーブ(モータードライバ)に「モーターを回しなさい」と命令を送る。
- スレーブが命令を受けてモーターを回転させ始める。
Modbusを使うときの注意点
| アドレス設定 | スレーブ機器ごとに「アドレス」という番号を設定しないと混乱します。 |
| 通信距離 | RTU(RS-485)は通信距離に限界(最大1200m)があるので注意が必要です。 |
| 速度の調整 | 使用環境に応じて通信速度(ボーレート)を設定します。 |
初心者がModbusを扱う前にやるべきこと
| 基本的な用語に慣れる | マスター、スレーブ、レジスタなどの意味を理解しましょう。 |
| シミュレーション環境を使う | PC上で動くシミュレーター(Modbusマスターツール・スレーブエミュレーター)を探して試してみましょう。 |
| 実機で試す | 例えば、ArduinoやRaspberry Piなどの安価なデバイスを使って、実際に通信を試すと理解が深まります。 |
合わせて読みたい
まとめ
Modbusは「機械同士を話させるための簡単なルール」と思えば難しくありません。工場の自動化や機械の制御で必要不可欠な存在であり、特にこれからPLCを勉強したい人にとっては、必ず押さえておきたい技術のひとつです!

